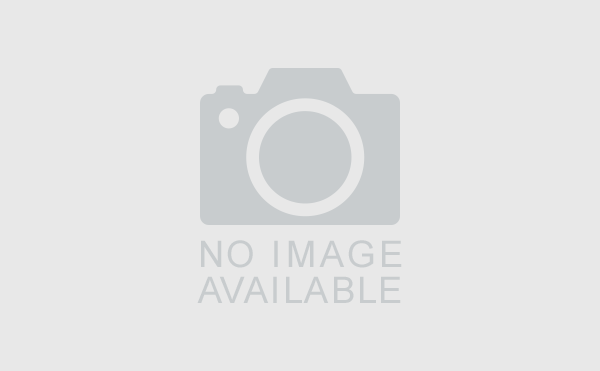思うこと:スティーブ・ジョブズのスピーチの読み方~私の場合
スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学で卒業生向けに行ったスピーチはあまりに有名です。
養子だったことの告白に始まり、Stay Hhungry, Stay Foolishで終わる、このスピーチは世界的に大きなインパクトを与えました。
全文はこちら。読んだことのない方は、英語の勉強にもなりますので、和訳と併せてぜひ原文で読んでみて下さい(和文は検索すればいっぱい出てきます)。
2005年6月の話ですから、もう12年前になるのですね。
当時、私は15年間勤めた銀行を辞める前、すなわち起業寸前のタイミングでもあり、彼の言葉には大いに勇気をもらったことを覚えています。
書感にはならないですが、私なりのスピーチの読み方です。
点が線になる話
大学に潜り込んで、カリグラフィー(英語の習字)を勉強した点。
そして、それがマッキントッシュ開発の際に、複数の美しいフォント(字体)が導入されるに至ったこと。
「ウィンドウズはマックのパクリだから、僕が中退していなかったら、カリグラフィーをしていなかったら、世界中のPCは退屈な文字だっただろう」と誇らしげに語っています。
・今やっていることは無駄ではないよ。振り返ったら、点と点は結ばれているんだ。だから、目の前のことを一所懸命やることが大切なんだよ。
道半ばだけど頑張っている人たちへのメッセージとして、これほど温かいものはないでしょう。
個人的にも、教育分野での起業を前にして、今までの銀行員での経験がどのような形でつながっていくのだろうと考えたものです。
Keep looking. Don’t settle.(探し続けろ。落ち着いてはいけない)
仕事というのは一生の中でも大きな部分を占めるので、好きなことをやるべきだ。
もし、まだ見つかっていないのであれば、探し続けるんだ。見つかるまで落ち着いちゃだめだ。
このスピーチ、最後のStay Hungry, Stay Foolish(ハングリーであれ、愚かであれ)が、よく引き合いに出されます。
が、これは雑誌からの引用ですし、ジョブズにしては少しお洒落すぎるように思えます。
私にはむしろ、仕事観について語る「Keep looking. Don’t settle.」の方が、彼の性格(執拗さも含めて)を示す心の声のような気がします。
スティーブ・ジョブズに感じる違和感
多くの人がスティーブ・ジョブズになりたいと熱狂的にあこがれる対象だと思います。
ただ、私自身は彼のようになりたいとは思わないのです。なので伝記も読んでおらず、この文章と見聞きした彼の業績だけからの感じ方です。
なろうと思っても当然なれないのでどうでもいい話なのですが(笑)
私が彼について推定するのは、
・成し遂げても成し遂げても、次を追い求め続ける。あそこまで追う人というのは、常に今に満足できない深い欠如をかかえてしまっているんだろうと感じます。
・昔、学校でconsist of とconsist inの違いを覚える時に、Happiness consists in contentment. というコトワザを学びました。「しあわせは満足にあり」ということになるのでしょうか。ちょっと辛気臭いのですが、私には納得感のあるコトワザです。
・心理的に「社会的成功は別として」も「ジョブズの人生が任意の一人(含む私)の人生より上等で幸せ」だと考えたくないのかなとも思います。
・ですが、成功者でも素直に尊敬できる人(人間愛にあふれるような動きをする人が多い)もいるので、やっぱり感性が合わないのでしょう。
天才をはぐくむアメリカの懐の深さ(=ユルさ・隙)
実は、私がこのスピーチの中で最も「そうなんだよなぁ」と納得感をもったのが、以下の部分です。
・大学中退後、寮を追い出されたので友達の下宿の床で寝ていた。
・毎週日曜に10キロ歩いて教会でご飯をもらいに行った。
・面白そうな授業を見つけては潜り込んだ。
そう、メインではない、本当に何気ない場面です。
でも、この友達がいなかったら、教会がこんなことしていなかったら、そして、その授業の教授がジョブズを追い出していたら(たぶん教授もわかっていたんじゃないでしょうかね)…
日本だったらこんな風になったのかな。やっぱりアメリカだからのような気もするな。
当時のアメリカの底流にあった「まぁ、困っているならしょうがないか」という“ユルさ”や“親切心”が、ジョブスを生み出したような気がしているのです。
そういえば、私も大学生時代、アメリカに語学留学中だった友人の寮に1週間くらい潜り込んだことがあります。
みんな友達になってくれて、部屋に見回りが来たら隠してくれたりしました。勝手にパーティーにも参加していました。
ちょっとしたズルって結束心を固めたりして。今、思い出しても、「なんかよかったな」と、とても気持ちが豊かになる思い出です。
良し悪しではなく、違いなのですが…
根がルーズで社会性に若干欠ける私なんかは、社会に流れる「緩さ」とか「隙」に時々あこがれます。
日本には色々なことが隙が無いように整備されて、それでガチガチに感じることが多いように思えます。
自分勝手な感想ですけど、世界中で一番「ガチガチ」な国なんじゃないですかね。
なんでもっと気楽にやれないのだろうか、と。
日本は、起業で失敗した場合のリスクが高い国と認識されているようです。
ただ、「だから、アメリカっていいんだよな」という話には当然なりません。
彼のような成功例はほんの少しですし、同様の状況だった人の多くが貧困に落ちて、それが連鎖して、犯罪につながっていると思われるからです。
で、格差は日本より大きい。ギャングものさばるし、不正も桁違いでしょう。
天才を育んだ緩さは、同時に社会の不安定さや非効率さも生んでいるとも言えます。
日本は仕組みも人も手堅いので、天才は生みにくいけど、それなりに社会は安定している(先延ばししているだけなのかな?)。
ですから、私は外国の事例が引き合いに出されるとき、
「多くの場合、いいとか悪いでは、一律的に判断できない。いい面もあれば、悪い面もあって、それは多くの場合セットになっている」
「だから、良し悪しでなく、“違い”として認識すべきだ。一概にもってくればよいというものではない」
と考えるようにしています。
PS: たまには「ユルく」もありかと思います。
「日本の教育は×××…。 だけど、北欧では〇〇で上手く行っている。だから、日本も〇〇すべきだ」的な議論も同様で、あまり短絡的に考えるべきではないでしょう。
美味しい話しには裏があることが多いですし、そもそもの風土に合うのかは検討すべきです。
ただ、個人的には日本の歴史を見る限り、
日本は「外国から謙虚に学んだ時に伸びる」傾向があると思います。
もちろん、時代のタイミングとか他国との関係など複雑な要因はあると思いますが…
そして同様に「伸びた後、過剰適応しすぎて自ら選択肢を狭める」、
その後「硬直化して、路線変更ができなくなる」ように感じます。
(どこの国でも同じなんでしょうかね?)
なので、時には素直に外国の好事例を導入してもいいんじゃないかと思います。
「和魂洋才」みたいな感じで、うまい具合にアレンジ(換骨奪胎?)していくのも日本のお家芸でもありますし。
時にはちょっと緩めて、チャレンジしてみてもいいのではないかと思います。
スティーブ・ジョブズからかなり離れて、すっごい緩い話になってしまいました。
<関連記事>思うことシリーズ
<堺谷武志の略歴>
大阪出身、京都大学工学部、南カリフォルニア大学MBA、三菱UFJ銀行を経て、キッズアイランド設立。保育士。一女の父。
(プロフィール詳細はこちら)
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村