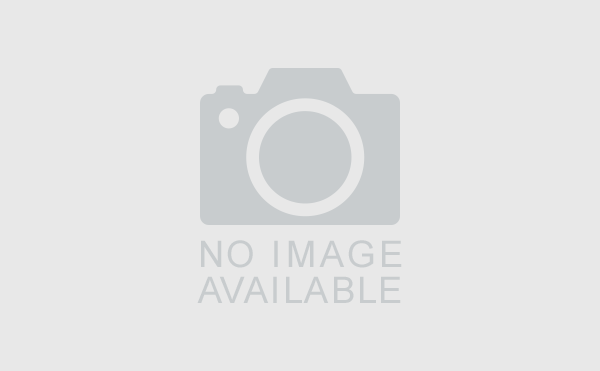キッズアイランドのこだわり:子どもの英語を評価しない理由
キッズアイランドでは、プリスクールの間はとっても総合教育的なのですが、
キンダークラス、アフタースクールになるにつれ、英語活動に力点がシフトしていきます。
とは言っても単に技術的なものにスポットを当てるだけでなく、Literacy、Music、Science、Story Reading、Workbook、そして時折Outdoorも交えながら、アクティビティーをベースとして英語に親しんでいくスタイルをとっています。
「ウチの子って、どれくらいできるんですか?」
とても楽しくていいクラスだと思います。レベル的にもかなり高いと思います。
そう、自画自賛です(笑)
子どもの英語は「細く、長く続ける」のが最も大切だと考えていて、「楽しさ」はその大きな理由になると思っています。
ただ、保護者の方から小学生くらいになると、こんな声もチラホラ…
「キッズアイランドが楽しいのはわかる。」
「幼い頃から、かれこれ6年くらい通っていますし。」
でも…
ウチの子って、どれくらいできるのですか?
そうなのです、キッズアイランドでは評価をしないスクールなのです。
最初に、誤解を招かないように、評価やテストをするスクールを批判したいわけではありませんので(それを励みに頑張ることは十分にあり得るので)。
ただここまで徹底した「評価しません主義」も少数派かなと思い、その考え方を少し説明したいのです。
評価はしません、でも、フィードバックはするんです
評価はしませんが、フィードバックの機会はいくつか行っています。
・クラス終了後の内容説明
・クラス参観(年に2回)
・半年毎のポジティブ・フィードバック(どんな活動が好きか、どんな態度で取り組んでいるか、何が得意か、などについてポジティブなトーンで記述してお渡し)
~フィードバックの方法論については今後も深掘りしていく予定です
それでも、英語スキルに関する「できる・できない」の評価、特に数値的な評価はしませんし、外部テストを受けることもお勧めしていません。
ですから、保護者からすると「費用対効果」が見えにくい習い事なのです。
(そんな中、信用して通わせていただいている保護者の方には本当に感謝しています。なかなかこんな寛容な目で見ていただけるスクールはないと思いますので。)
過去に何度か「評価、入れちゃおうかな」と考えなかったわけではありません。
その方が圧倒的に楽なんですよね。下世話な話ですが、宣伝などでも「〇才で英検□級合格!」と打ち出した方がわかりやすいでしょう(笑)

それでも、私たちは「評価をしない方針」にこだわってきました。
なぜか?
なぜ、子どもの頃に英語を学ぶのか?
理由を詳しく説明する前に、そもそもなぜ子ども時代から英語をしているのかを振り返らせて下さい。
それは、「長期的な視点でバイリンガル(英語をエンジョイできるレベル)になるため」です。
今、目の前でどれくらいできるかのためではありません。
詳しくはこちらのブログをご覧ください。バイリンガル教育:「英語が話せて損をしちゃったよ」という話
日本の教育を受けながらバイリンガルになるには、以下が大切だと考えています。
- 小さい頃から始めた方がよい(耳がいい、心に壁がないetc.)~特にリスニング
- 20歳前後にかなり使えるレベルを目指す(長期的な視点で考える)
具体的には「海外の大学・大学院で科目を学べるレベルを目指す」ことをお勧めしたいです(もちろん最後は本人の頑張り次第ですが、親ができる準備として)。
詳しくはこちらのブログをご覧ください。バイリンガル教育:0~6歳で押さえたい3つのポイント
もう一つ意識しておきたいのは、「実践的な英語コミュニケーション力が大切」ということです。
- 「テストで高得点でも、コミュニケーションできない人はいっぱいいる」ということです。
詳しくはこちらのブログをご覧ください。バイリンガル教育:「学校英語」VS「実践英語」
つまり、なぜ子どもの頃に習うかと言えば、「大人になった時に役に立つツール」、つまり「英語でのコミュニケーションスキル」の基礎を長期的な視点で身につけるためです。
そこから逆算して、また子どもの特性(特に耳の良さ!)を踏まえて、0~6歳、7歳~12歳で何に重点をおいて活動するべきかを踏まえて設計すべきだと思うのです。
で、その流れでは「評価は不要。いや、むしろ逆効果」であると考えているのです。
評価をしない5つの理由
ここで評価に話を戻しましょう。小学生レベルで評価をしない理由は以下です。
1.子どもの英語のスキル評価は難しい(測りたいことが測れない)
- いったい何を評価するというのでしょう。本当に測りたいものは、意欲であったり、取組み姿勢であったりなど測れにくいものばかりです。
- 逆に測れるモノは大したものじゃない。ガチョウの金の卵の逸話と同じで、大人から見た目の前の成果を追っていてはロクなことになりません。
2.子どものやる気をくじくリスクが高い
- 評価とは結局「できる」「できない」を仕分けることです。そして、対策をしようとすると「できない」ことに目が行きます、大人も子どもも。
- 子どもの英語には「絶対的な安心感(間違っても全然オッケー)」が必要です。実は英語だけじゃなく、評価されるとほとんどの子どもはやる気をくじかれます。
3.わからないことも(こそ)学びだと伝えたい
- 特に第二外国語としての英語は「いつまで経っても100%わかるのは至難の業(ほぼ無理!)」です。だから、わからない状況とは一生のお付き合いになります。
- だから「わからなくても大丈夫」ということを肌で感じてほしい。これを評価によってくじいていたら、子どもの芽を摘んでしまうことになります。
4.実践的なアプローチをしたい
- 実践的なコミュニケーション能力は、試験対策をしても身に付きません。まずは聴いて理解する力。これを小さい頃からナチュラルスピードでやるのがとても大切です。
- 実践では繰り返しになりますが、「わかる範囲で何とかする」「わからないことに慣れる(びびらない)」ことも大切です。そんなときに評価は邪魔になります。
5. 細く、長く続けるサポートをしたい
- 結局、子どもの英語は「細く、長く」続けることにつきます。評価されることで英語嫌いになる子もいます。いくら頑張っても止めたら、そこで大幅ロスです。
- 6歳まではとにかく聞くこと、繰り返すこと。12歳までは聞くことと読むこと。ここにいかに楽しみながら(イヤにならずに)時間を費やせるかが大切だと考えます。
- 中学で文法をサラッと固め、中高大でより実践的な対策(シャドイングや多読)を行っていく。これができれば、高いレベルで英語コミュニケーションが身に付きます。
コミュニケーションという観点から考えますと、
単に語学的スキルの高い低いだけではなく、相手を受け入れる姿勢、自分を信じる姿勢、楽しむ気持ち、身振り、手振りなど「総合的な行為」です。
保護者の方は、特に「話せるようになってほしい」と思っていらっしゃいますが、これは本当に難しいです。
子どもを英語嫌いにさせるのは簡単です。
「ほら、しゃべってみなさい」と繰り返させて、そして訂正していれば、あっと言う間に話せなくなります。
100聞いて、1しゃべるくらいの意識が必要です。
できる・できないの評価は中学生からで十分
ですから、小さい頃には、「できる」「できない」の切り口ではなく、「楽しいね」「びびらなくていいんだよ」と言った感覚を後押ししたいなぁと思っています。
そもそも論として、低年齢の子供たち、特に10歳以下に対して評価をするのは、デメリットの方が大きいと思います。
どうしても評価すると、評価基準との比較に大人も子供も意識が集中してしまいますからね。
評価の目的自体が元来そういうものですし。
親も「4級に受かったら、次は3級」「次は準2級…」などと、子どもができなくなる地点にたどり着くまで張り切っちゃったりしますから(笑)。
子どもはそれで疲弊していく…
コミュニケーションの楽しさより、評価を求めることが優先されがちです。そして、英語嫌いにしてしまう。
と、くどくどと子どもたちの評価しない理由を書いてきたのですが、本当はわかっているのです。
保護者の方が評価を欲しがるのは当然のことだと。
でも、すみません。キッズアイランドでは、子ども目線を優先させていただいています。
私が子どもだったらとこう考えます。そして、それを大切にしたいです。
ゴチャゴチャ言わないで! ボクはただ面白い外国人ティーチャーとアクティビティーを楽しみたいだけ!(笑)
小学生まではこの意欲・スタンスこそ大切。そして結果として、コミュニケーション能力がついていくのであれば最高だとお考えいただければと思います。
PS: 本当に評価したいこと
ちなみに、キッズアイランドの名誉のために申します(笑)が、評価しないからと言って、英語スキルが低いわけでは決してありません。
むしろ高いでしょう。コンテンツ面での要求水準はかなり高いですし。また今度プログラムを紹介しますね。
キッズアイランドでは、2歳から来たお子さんが、幼なじみと共に継続的に学ぶスタイルです(一貫プログラムがあります)。
レベル維持のために途中入会を受け入れないシステムを取っているところはほとんどないと思いますが、これが効果を上げていると思います。
おかげで、「とにかくやめない」というだけで英語獲得の効果はかなり高いものがあります。
正直レベルは様々です。英語神経(運動神経的なもの)、宿題をどの程度しているか、家庭学習、など色々な要因でレベルは変わってきます。
が、漏れ聞いた話として…(よくできる方の人たちが多いですが…)
- 小1で引越しして、B社に行ったが小4の経験者クラスでもレベルが合わないと言われた。結局通学大変だけど戻ってきた(ありがとうございます)
- インターナショナルスクールのアフタースクールに移ったら、通常クラスではレベルが合わず、帰国子女クラスに入ることになった。
- 小学校3年生で英検準2級に合格(小2で3級、小3で準2級。これは宿題もかなり熱心にしていた例外的によくできるお子さんです。英検対策はゼロと言っていました)
- 「他を探したのですが、ここ以上に楽しめるところがなかったんです」という、「他、探したんかいっ!」と突っ込みたくなるような正直すぎる告白もありました。(笑)
私の感覚としては、小3~4の平均的な生徒なら英検だとおよそ3級くらいは合格するかなという感じです(あくまで感覚です)。
先日、小6まで続けたお子さんで「週一回の通学と宿題のみ、対策なしで準2級(リスニングは2級レベル)」という報告をいただきました。
(詳しくはこちらのブログをご覧ください。キッズアイランドの自然体での英語力)
名門校ですが、クラスで一名だけだそうです(他クラスで帰国子女やハーフのお子さんが2級を取得)
このお子さんはよくできましたので妥当なラインです(小6だと内容的には高校レベルのことをしているので)
それとリスニングレベルが高いのが小さい頃からやっていた人の特徴ですね。
小学生生活を楽しみながら、他の趣味や習い事もしっかり楽しんで、かつ、英語も楽しみながら自然体でここまでたどり着いてくれました。
(ちなみに、こういうことを書くと「ウチのスクールは小学〇年生で□級通りました」とかいう方がいらっしゃると思います。それはそれでいいと思います。ただ、その「低年齢で高い級を取りました!」競争に乗るつもりは全くございません。)
それより、本当に評価したいのは次のようなことです。
「1つのことを10年間続けたことの大切さ(13歳にしてw)」
「できることの自信」
「ナチュラルスピードの英語をたくさん聞いた。なので、生の英語もなんとなくわかる」
「わからなくても楽しめる心の余裕」
「長文でもひるまない」
「ロックやポップスの名曲たくさん覚えた」
「アメリカの理科の教科書、なんとなく理解できる」
「世界って広いな」などなど
実践に近い経験から生まれた「広くて大きな基盤」ができています。
これらが「大人になった時に実践的なコミュニケーション能力」のベースになっていくのです。
こんなの小学生段階で評価できないと思うのですよ。
<堺谷武志の略歴>
大阪出身、京都大学工学部、南カリフォルニア大学MBA、三菱UFJ銀行を経て、キッズアイランド設立。保育士。一女の父。週末登山家。
現在「都会の子どもに『ソダチバ』を!」プロジェクト推進中
(プロフィール詳細はこちら)
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村