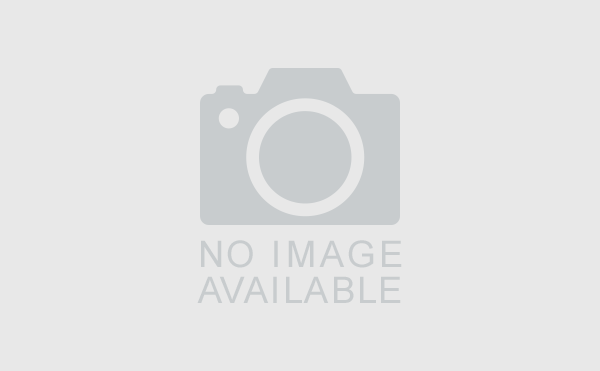書感:アメリカ関連の教育の本
アメリカの教育がどんな状況なのかを知りたくて、何冊か本を読みました。

①脱学校の社会(1977年)
②学習する学校(2014年)
③崩壊するアメリカの公教育(2016年)
④アメリカの教室に入ってみた(2017年)
⑤アメリカの学校教育(2017年)
これに以前読んだ「⑥ブレンディッド・ラーニング」を入れていいと思います。
まず、②はすごい本です。色々な意味で、これぞアメリカという本。
900頁近い大部で読むだけでも大変、1か月くらいかかりました。
これを訳されたリヒテルズさんは魔法使いじゃないかと思います。すみません、くだらないことを言って(笑)
心から感謝いたします、これ英語だったら私の根性だと読めなかったと思います。
読まれている方が多いと思いますが、心ある教育者は必読かと。
①は彼自身はアメリカ人ではないですが、70年代後半という早い時期に「学校という仕組みから抜け出すべきだ」という発想を世に問いかけた人です。
②と⑥から、合理的・実践的なある意味典型的なアメリカのアプローチで新しい方法が書かれています(もうすでに新しくないのかもしれませんが)
②の中で、「システム思考」が特に興味深かったです。
③④は、アメリカの教育改革の過程において、特に貧困地域を中心に「公教育が崩壊している」という厳しい現実を記してくれています。
アメリカは極端な国ですね。良いも悪いも、日本人のスケールからはずれてくる。
エリートを生む仕組みではかなわない、一方で、ひどい地域のひどい状況なんて日本の想像を絶する(教育の前に治安というレベル)
教育というのは人の営みであって、やはり複雑なので、理屈が魅力的に聞こえてもなかなかその通りにはいかないものだと再認識しました。
特に、政治家やビジネスマンの感覚にすっきりとフィットする意見は、逆に一呼吸おいた方がいいかもしれません。
一方で、アメリカから取り入れるべき点は、本当に山のようにあると思います。素直にやりましょう。
日本の傾向として、急いでやっても周回遅れのパターンです。
しかし、これを読むと、バランスから考えて、やはりヨーロッパの事例が日本には参考になるのでしょうか?
(デンマーク、オランダ、フィンランド、スウェーデンあたり?これからまだまだ読まないと)
教育関係者は②③④、一般の方は④をお読みになることをお勧めします。
以下、個別論です。
<脱学校の社会>

現代アメリカは、学校という仕組みに絡めとられている。これはスクールだけではなくて、社会全体がそうなっている。
脱学校(deschooling)を行うべきである。
学びを人々の手に取り戻すべきだ。
これは、合理主義・個人主義のアメリカ人のハートには響くのだろうと思います。
<学習する学校>

長くてつらいという人は、まず第2章に絞って読むとしてもいいかもしれません。
長いので、間をおいて読むと、Where am I?となりますので。
とは言っても、5つのディシプリンを挙げておきます。
メンタルモデル、システム思考、チーム学習、共有ビジョン、自己マスタリー
私はこの中の「システム思考」が面白いと思います。複雑系の現実をどうシミュレートしていくかというアプローチと私は理解。
現実とは、問いと答えが一対一になっていなくて(これも重要)、複数の要因が絡み合いながら一つの現実に影響を与える。
これを、小さい頃からゲーム感覚でやっておくと、数学やプログラミングになじみやすいと思います。
STEMや探求型にぴったり。ただ、教えるのが大変そう。
この本のようなことが高いレベルでできている学校があるとすれば、それはすごいことで、ちょっと日本はかなわないと思います
<崩壊するアメリカの公教育>

上記の「学習する学校」はすごいのですが、一方で本当にそんなことってできるのと感じました。
題名の通り、崩壊する公教育について特に貧困地域で詳しく述べています。
学校区(School District)というアメリカ独特の制度があって、地域ごとの裕福さが学校予算へ反映されるため、そこが公教育の公平性を損なう根っこになりうると思いました。
これを読むと、日本の教育改革も気をつけないといけないと思います。
政治家や経済人が「それ、いいじゃん」と言うもの、現場に下ろした時に本当にそうなるのか、何か落とし穴はないか、ということを考えておくべきだなと思いました。
これは、教育関係者だけではなく、全ての保護者がです。
この点(特に経済原理・競争原理の安易な導入には気をつけようね)が、作者のメッセージ・警鐘かなと私は受け取りました。
まあ、日本の場合、そこまでひどくはならないと思いますが。
<アメリカの教室に入ってみた>

研究でアメリカに駐在された著者が、自分のお子さんを学校に入れることで、図らずもリアルな学校の実態があぶり出された形の詳細レポートのようになっています。
貧困地域の公立校と小規模な私立と2校行かせたために、よりその差が浮き彫りになってがく然とさせられます。
分析がとても深くて、示唆になる考えがあります。
例えば、成績が悪い貧困地域の学校では、実は年中から計算問題を解かせたりしている。だけど(だから?)、成績が上がらない。
一方で、私学は友だちとの遊びを促すような活動が中心。結果的には勉強もできるようになる。
アメリカでは、見た目、宗教などあまりに違いが大きいので、違いが当たり前と受け止められ、それが前提とされる。
日本は見た目を含めてお互い似過ぎているので、少しの違いも目立ってしまう。
同じ「多様性」や「インクルーシブ」の話をしていても、前提からして確かにずれてきそうです。
<堺谷武志の略歴>
大阪出身、京都大学工学部、南カリフォルニア大学MBA、三菱UFJ銀行を経て、キッズアイランド設立。保育士。一女の父。週末登山家。
現在「都会の子どもに『ソダチバ』を!」プロジェクト推進中
(プロフィール詳細はこちら)
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村