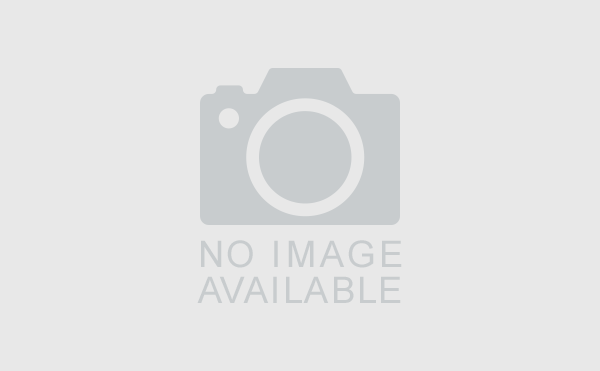子育てサプリ:目指す子ども像を越えて~中からあふれるものを大切に。
教育関連の言葉がいちいち苦手です(笑)。
また、私の面倒くさいひねくれた性格が頭をもたげるのですが...
例えば、「明るく元気な子どもを育てます」といった標語…
まあ、ご立派でと思うものの…
「では、明るくない子はダメなのか?」とか
「元気じゃなければ認めてもらえないのか」とか、つい反論したくなってしまいますw
違う流れで「どんな子にも探せば一つくらい良いところが見つかる」という言葉にも同様の抵抗を感じます。
「一つもなかったらどうするんじゃい?そしたら生きてたらアカンのか」
「その『良いところ』やらを決めるのはあなたなのか。あなたは神か」とかw

気持ちはとってもわかります。いずれも全く悪気はないと思います。
ですが、その悪気のないのが私にはリスキーな感じがするのです。暗黙の了解として大人は偉いと思っていて、謙虚さに欠けると思うのです。
なので、私は標語とか大人が示す子ども像の反対派。
高等教育では標語はありかも知れない
高等教育、例えば、大学などで「リーダーシップのある人間をつくる」とか「グローバルな競争力を育てる」などの標語。
これは、カリキュラムの具体的な内容や担い手が伴っているのであれば、ありだと思います。
大学や学科を選ぶ成人前後の人間が相応の判断力をもって、自分で選択するわけですから、そこには明確な旗印があってしかるべきでしょう。
ただ、ちょっとシニカルに言うと、
「まあ、そうおっしゃるからには、そちらの研究者・教員はみなさんリーダーシップがバリバリで、グローバルに通用される方たちばかりなのでしょうね」くらいのツッコミは入れたくなります(笑)
「受け入れる→応援する→時間をかけて伝えていく」の3ステップ
標語というのは担い手の目的意識をまとめるのに便利なのですが、教育の場合はなにかそぐわない気がします。
では、標語(=大人から見た“よい子の基準”)の替りに何を使えばいいのか?
そんな便利なものはないっw
あるとすれば、自分達の行動基準のようなものでしょうか。
愛情をもって一人ひとりのすべてを受け止める
自分らしさが大きな幹になるように応援する
ルールとか価値観は時間をかけて伝えていく
偉そうにされて、できていないところをつかれてばかりじゃ、子どもじゃなくて大人でも誰もがやる気を失いますよね~
だいたい、たいしたことがない人ほど偉そうにしますし(笑)
さきほど「大きな幹になるように」と書きましたが、ぜひそうなってほしい。
大木になるポテンシャルがあるのに、刈り取られてこじんまりした盆栽になってしまうのは残念です。
特に、小さい間は「中からあふれるもの」を大切にすることが大切だと思います。
お勉強で得られるモノは、後からでもできる。
幹が育ってから、枝葉は世間にもまれていい感じの枝ぶりになっていけばいいのです。
中からあふれるもの(=もって生まれた性格)というのはかなり強くて、しつけや教育で何もかもを強制しようとするのはかなり無理のあるアプローチだと思います。
(過去ブログをご参照 三つ子のお母さまにおしえていただいたこと)
「教育の限界をわきまえつつ、その効果を追い求める」
私がある方から学んだ教えで、大切にしたい考え方です。
そのために、大人が(子どもではなく)自分たちを変える努力をする。
大人が変わらずに、教育をちょろっといじって子どもを変えようとするのは「厚かましいにもほどがある」と私は思っています。
標語なんぞに頼らない地道な取り組みが、特に10歳くらいまでの子どもの教育において大切なのではないか、そのように思っております。
<堺谷武志の略歴>
大阪出身、京都大学工学部、南カリフォルニア大学MBA、三菱UFJ銀行を経て、キッズアイランド設立。保育士。一女の父。週末登山家。
現在「都会の子どもに『ソダチバ』を!」プロジェクト推進中
(プロフィール詳細はこちら)
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村