バイリンガル教育:学校英語 vs 使える英語
学校での英語教育のあり方がどんどん見直されていて、素晴らしいことだと思います。
日本の教育ではどうしても「大学の受験対策」が優先されるところもありますが、今回の教育改革実施計画でそこもかなり踏み込んでいるようですので、長期的には大きな効果が期待されるところです。
(英語嫌い予備軍の子どもにとっては、更につらくなるでしょうが…)
「教育改革」実施後も学校英語はあくまで基礎
一方で、逆に心配になるのが、「これでようやく日本人は英語をしゃべれるようになる」という誤ったメッセージを世間に伝えることにならないかということです。
英語教育に携わっている方々であれば、以下のことはおそらく共感いただけるのではないかと思います。
・教育改革実施後も学校英語はあくまで基礎にすぎない
・例えば、高校卒業時の目途である英検2級(~準1級)だと楽しく旅行したり、外国人に道案内くらいはできるようになるだろう
・しかし、ビジネスで使えるレベルになるには自助努力が必要である
この辺りが世の中にしっかり伝わっていないと、何年かして「こんなはずじゃなかった」という声が起こりかねないと思います。
何を知らされておくべきか?
「音楽の授業でピアノを弾けるようにはならない。弾けるには、幼少期から毎日練習をする」
「甲子園に行くには、体育の授業では不十分。強豪校に入って毎日ハードな練習をする」
何でもそう、公教育で得られるのは基礎の基礎に過ぎないということです。
英語をツールとして使いこなせるレベルになるには、追加での訓練が必要です。
ですから「学校英語」と「実際の英語」には当然ギャップがあります。
ギャップの中で一番大きなものは、私の考えでは「会話のスピード」です。
(本当は全てなのですが、言い出すときりがないので絞ります)
大人になったらリスニングは苦行?
大人になってからのリスニングは本当に苦行です。
他のことと違って努力の割には成果が上がりにくい。効率が悪い。
少なくとも私にとってはそうでした。
就活や会社などで必要に迫られて試験を受ける方も多いでしょうが、
多くの大人が何といっても苦労しているのはリスニング対策ではないでしょうか?
個人的には、視力が悪いのにメガネ無しで凝視しているような、歯がゆく虚しい思いを何度も感じました。
本当に聞けるようになるのか、テストの期限もあるのに… 仕事も忙しいのに…
困ったあげくに「聞き流すだけで話せる…」的な教材に手を伸ばして挫折。
こういった無駄は社会全体で見ると日本の大きな損失だと思います。
リスニングを鍛えるのは若い方がいい
苦労の末にようやく高得点をとっても、本場に行ったらショックを受けるでしょう。
ネイティブは誰も、英検やTOEICのような話し方はしてくれない。
とにかく速くて聞き取れない…
その上、あのスピードに割り込んで話すなんて、とてもとても…
英語のリスニング力をつける際に何が問題かと言えば、
若い頃でないと効率がガクンと落ちてしまうということです。
小さい頃からやっている子どもは、リスニングで点数を稼いでいくことが多いようです。
文法は苦手だけど、リスニングは内容を話してくれるので簡単、とのことです。
ですから、リスニングについては本格的にやりたいなら大学でどうぞ、という話にはなりにくいのです。
ここが他の科目と違うところではないでしょうか?
私は、英語は突き詰めると、「音」と「意味」の2つに集約されると考えています。
この2つでどうロジックを取り、どうロジックを組み立て、どう伝えるかということかと。
ですので、まずは「音を取る耳」がとても重要です。
耳に関しては、音楽を学ぶには若い時の方が有利なのと同じで、英語の音も早期からの方が有利でしょう。
少し話はずれまますが、
私の実感では、音楽ができる人は英語の音を取るのも上手なように思えます。
多分、音の高さ、ピッチ、強調、音色などの感性が高いからだと推定します。
それと、全般的に女性の方が男性よりも英語(特に発音)が得意なような気がしています。
なので、音楽のできない男の子、ガンバレ!(私がそうでしたというだけの話で科学的根拠はないですけど(笑))
確度の高い方法は、ある程度見えているはず
英語の達人と言われる方などの著作を読みますと、
・若い頃に、とてつもない勉強のボリュームをした
・色々試した結果、こんな方法が自分には合っていた
・そして、今でも勉強している
と書かれています。
そうなのでしょう。安易な方法はないということです。
英語に限らず、「楽してできること」は、その程度のものでしかないのだと思います。
ただ、楽な方法はなくても、確度の高い、効率的な自主練方法はありそうです。
それは、専門家の間でおおよその意見は集約されるのではないでしょうか?
-
小さい頃から始めた方がいい、とか
-
シャドイングが効果的、とか…
小さい頃から成人までの、目的別やレベル別にあった形での訓練方法や教材などが、
学校などある程度オフィシャルな形で開示されていくと、日本全体にとって大きなプラスになりそうな気がします。
自助努力が必要な分野ではあるという認識
とは言っても、「学校英語では不十分ですから、あとは自分で対応してください」とは、学校の先生もオフィシャルには言えないでしょう(笑)
ただ、保護者の方には、
- 学校に期待できること、と
- 自助努力(親も含めて)が必要なこと、を
きっちりと分けて理解していただきたいと思います。特に、後者をしっかりと認識しておくことです。
例えば、アジアの多くの国では公教育は日本ほど強くありません。
その代り、お金持ちは英語の家庭教師をつけたり、留学をさせたりと親が様々な自助努力サポートをしています。
エリート層の子どもの多くは、当然のように英語を話します。
そのうえで、「何をどうするんですか」というのが彼らのテーマであって、
英語をどうしようかというレベルの話ではないのです。
インターネットの普及で、アジアだけでなく全世界的に子どもたちの英語や
その他のスキルへのアクセスはどんどんと向上していくことでしょう。
彼らは、あなたのお子さんの将来の仲間であり、競争相手でもあります。
「学校での英語」を「使える英語」にレベルアップするには、
授業以外に「自己鍛錬」と「ネイティブとの生のやり取り」がどこかで必要になります。
この2つを学校外で、つまりご家庭の自助努力で、いつどのタイミングで、
どのようにして補うかは意識しておいた方がいいのではないかとは思います。
PS:
今回は英語ができるようになるにはという観点でお話ししましたが、
英語ができなきゃいけないということでも、
英語ができればそれでいい、というメッセージでは全くありません。
できるにこしたことはありません、という程度の話です。
人生も豊になりますし、仕事などの舞台が広がります。
ただ、このように身につけておいた方がよいこと・分野はたくさんあります。
スポーツ、音楽、理数的な考え方、コミュニケーション能力、自然との触れ合い、協調性…などなど、数え上げればきりがありません。
それに、全員が野球選手やピアニストになりたいわけでも、なれるわけでもありません。
色々なことを試しながら、
好きなこと、できることなどを見極めながら、
最終的には本人が道を選んでいくべきです。
突き詰めると、この「色々と試す」という機会や環境を整備してあげるのが
親ができる精一杯のことなのかなと思います。
その中で、音楽、英語、スポーツは、人生を豊かにする意味で、
素地としては幼い頃からやらせてあげた方がいいような気がしていて。
そして、
一部の人にとって英語の切実度というのは
10年後20年後、今なんかよりもっと高くなっているような気がしていて…
それで少しお節介を申しあげているような次第です。
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村

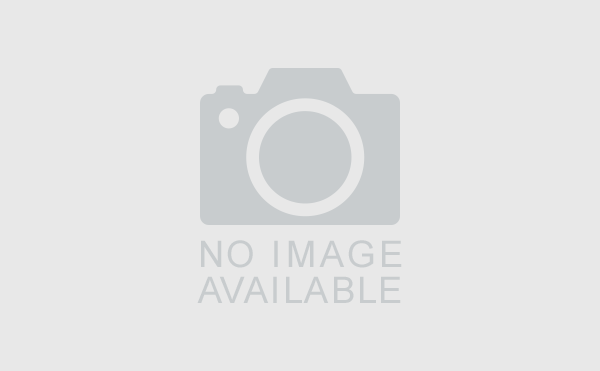
“バイリンガル教育:学校英語 vs 使える英語” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。