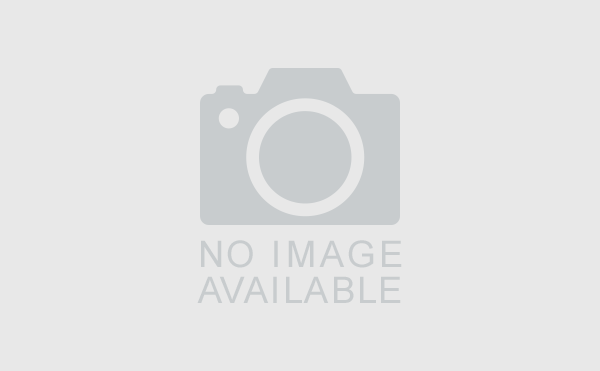コロナで進むパパの育児参加⇒世の中よくなる!
コロナで進むパパの育児参加
先週、個人面談をしていたのですが、今までにないことが2日連続でありました。
それは面談にパパだけが参加したことです。
今まではたいていがお母さんのみ(平日昼間なので)、あとたまに夫婦でお越しになるご家族はあったのですが、今回はパパだけが二組も!
トイレトレーニングの話とか、家での様子などとても具体的な話をされていました。とても新鮮。
下のお子さんの出産があって、コロナで病院に出入りもできず、ただひたすら子どもとサシで向き合う生活をしたんですね。
「本当に勉強になりました」といっていました。
この方が超有名外資系で働いていらして、テレワーク最先端。
まあ、これですよね、できる人というのは。どんなことも学びの機会にしてしまう。
仕事もバリバリ、家事・子育てしっかり、かと言ってこじんまりした感じではなく、大物感ただよう方です。
時代は変わってきているのだなと思いました。
育児で大人が育つ
育児参加はママのサポートみたいな文脈で語られることが多いですが、それもあるけど本質は全然ちがいます。
本当は地域みんなで育てるものですから、実はパパだけでは足りない。とはいえ、地域社会弱体化の今は夫婦で育てるが現実的な選択肢でしょう。
あと、子育てと言いますが、育つのは子どもだけではありません。
大人、特にパパが人として成長する絶好の機会なのです。
仕事って効率性重視だけど、子育てって真逆でひたすら見る・待つの非効率な世界。
子どもの時間って、本当にゆったり流れていきます。
赤ん坊なんか、ずーっともじもじしてたり、飲んで、寝て、泣いて、でも、永遠に感じるくらいスローな時間が流れます。
その意味では、目に見える生産性はゼロ。笑
赤ん坊に「来月のミルクのノルマは2倍な」「すぐ泣くの禁止」と言った大人の理屈は通じない。笑
とにかく彼・彼女のペースにすべて合わせて対応するしかない。究極の子ども思考。
で、この非効率だったり、合理的でなかったりすることにじっくりつきあうことが大切なのではないかと私は思います。
現代の大人って、どうしようもないくらい何かに追われる感じで時を過ごしています。
ほとんどの時間を、「合理性」「効率性」「損得」といった狭くて、ある意味「直線的な価値観」の中にどっぷりつかって過ごしています。
でも、子育てで必要なのは異なる価値観です。
効率よく「一回で覚えなさい」と言っても子どもの心には響きません。
大切なのは「もういっかぁ~い!」と言われながら、百回くらい繰り返すことにつきあうことだったりするわけです。
子どもの相場観を肌で感じる
また、「子どもってこんなもんだ(泣くもんだ、うるさいもんだ、そして、かわいいもんだ)」という子どもの相場観をわかること、これはとても大切です。
そして、これほどまでに「人から切に必要とされていること」「つぶらな瞳で見つめられること」があるんだと知ることは深い喜びです。
忙しくて忘れそうになっている気持ち「目の前だけの現実(仕事とか)がすべてじゃないんだ」と感じることは視野を広げます。
でも実は考えてみたら、子どもはとてつもなく成長します。
0歳から3歳までの間に「寝転んで泣く肉の塊り」から「歩いておしゃべりする怪獣」にまで、とてもつもない速度で成長をするわけですよ。笑
スローに見えても、本人たちは一瞬一瞬を「生き抜くために必死」です。
全力でミルクを飲んでいます。我々はビールにあれほどの情熱をささげているでしょうか?
必死でいろんなものを見ています。スマホを流し読みしているのとはわけが違います。
かわいく見えるのも、保護してもらうための戦略かもしれません。笑
とにかく今を真摯に生きていて、「成長性」「態度・姿勢」「戦略性」いずれをとっても、かなう大人はいません。
だから、大人は子どもから学ばなきゃいけないのです。
むしろ、人生を学ばせていただく絶好の機会で、仕事なんかしている場合じゃない、と。
これからは「えー、君、育児しなかったわけ?出世は厳しいね」と言われる時代が来ることでしょう。笑
未来の『共感社会』をつくる
元々、人類の子育ての特徴は、最近では忘れかけられていますが、「共同保育」だったそうです。
類人猿は子どもが2年くらい母親にしがみついて育てるのですが、人間は頭がでかいし、握力もないので、下に置いて育てる。
泣いたらライオンに食べられないように、誰か(母親に限らず)が抱いて逃げる。
そうやって、幼い子どもをみんながいつくしむことで、通常母親しか持たない母性的な感性を集団が獲得していった。
それにより「共感社会」を形成し、その社会性により発展していった。
つまり、人類の強みの要因は「男性の(というか一族・近隣全体の)育児参加」だったわけです。
近代以降、特に昭和は、工業化、都会化、職住分離、企業戦士化などで男性の育児参画が明らかに減りましたが、こんなのは数十万年の人類史ではたかだか50年くらいの話です。
そして、コロナが来て、テレワークになったりで、子どもとの接点が増えたパパが多くて、改めてその大切さを認識している家族が増えています。
これは、日本全体にとって喜ばしいことだと思います。
未来は「共感社会」まっしぐらです。
そして、これを機に「教育をも見直し始めた家族」も多いようです。
コロナでモタモタしている幼稚園・学校の現実を見たり、あるいはじっくりと子どもと接したりする中で、
改めて「教育って何?」と深く考えてみて、「あれっ?教育ってもっと真剣に考えないといけないのと違うん?」と気づき始めています。
コロナを機に色々変わっていく…日本の教育もその一つかもしれないなと思っています。
PS:
子育ても今のうちですよ。あっと言う間です。
うちのように18才になったら、まっすぐ見つめてくるつぶらな瞳も、甘えた「ペァパァ~」みたいな声もどこかへ行ってしまいます。笑
ぜひ今のうちに精一杯楽しんでおいていてくださいね。笑
というわけで、今回は
・コロナでパパのマジ育児参加が増えている
・育児は人のためならず、大人の成長の絶好の機会
・未来の日本の共感力、教育力は上がる(かもしれない)
というお話をしました。
少しでも参考になればハッピーです!
<堺谷武志の略歴>
大阪出身、京都大学工学部、南カリフォルニア大学MBA、三菱UFJ銀行(海外駐在やアジア戦略担当)を経て独立。2006年インターナショナルな環境で人と自然にふれあうプリスクール「キッズアイランド」設立。保育士。一女の父。東洋拳法二段、京都伝説のアマバン「コンプレックス」のボーカル。週末へたれ登山家。
2019年教育起業家とともにNPO法人ソダチバ・プロジェクトを設立し、代表理事に就任。幼稚園でもインターでもない第三の選択肢「HILLOCK Kinder School」を設立。2022年4月「ヒロック・オルタナティブ小学校」を設立します!
(プロフィール詳細はこちら)(ヒロックの想いはこちら)
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村