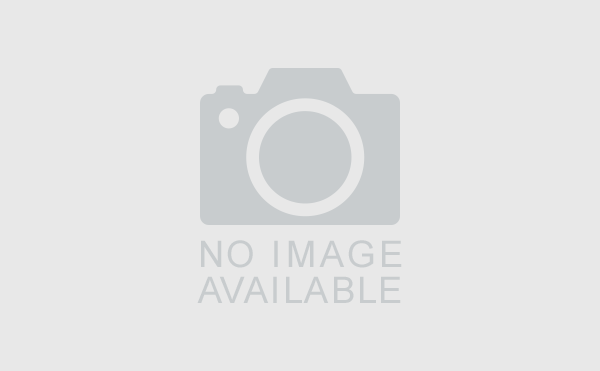日本の教師の技術に関する本
教育関係の方は、いずれも読んで間違いのない本だと思います。

授業の腕を上げる法則
教室ファシリテーション
アクティブ・ラーニングを考える
よくわかる学校現場の教育心理学 AL時代を切り拓く
赤坂版「クラス会議」完全マニュアル
新版 授業の腕を上げる法則(向山洋一)
一斉授業時代の教育技術を広めた小学校教師の本。授業の原則10条を示し、その後具体的な技術を紹介している

例えば、第1条(趣意説明の原則)では以下の趣旨を述べている
ごみを拾わせるとき、「ゴミを拾いなさい」という号令をかける人がいるが、号令は兵隊にかけるものである。子どもは兵隊ではない。
「教室を見回してごらん。もう少しきれいにしたいね。自分がこうしたいと思うことをしてごらん。時間は5分」こう言えるのがプロの技術である。
このほか、
・跳び箱を「全員に」飛ばせる技術、子どもが何をしてほしいかのアンケート結果、などの話をはじめ、とても興味深い。
・教師の教える技術に焦点を当てた運動を進め、情報を共有するデータベースを作っていらっしゃいます。
私は、本当に立派な方だと思いました。
アクティブ・ラーニングを考える

アクティブ・ラーニングについて、色々な人が色々なことを述べている本。
そうなんだろうとは思います。こんな形で現場に投げられるのかなぁという感じ。
教室ファシリテーション10のアイテム 100のステップ(堀裕嗣、2012年)
よくわかる学校現場の教育心理学 AL時代を切り拓く(堀裕嗣、2017年)


この2冊は、私が勝手にフォローしている北海道在住の中学国語教師の本。
前者は、アクティブ・ラーニングで使える技術が詳細に提示されている
後者は、「これからアクティブ・ラーニングの時代になるけど、あんたら大丈夫、覚悟はできてる?」「かつ、その先もみすえておかんとアカンのよ」というメッセージを、心理学を踏まえて提示している。注:ご本人は関西弁ではありません(笑)
赤坂版「クラス会議」完全マニュアル(赤坂真二)
クラス会議を通して、解決能力をつけていくための運営の仕方

意見をやり取りすることはとても素晴らしい。教師→生徒の一方通行からの脱却を図るのに効果的な方法だと思います。
職員会議や、大企業の会議の運営も、ぜひこの本を読んで忠実にやってほしいと思います(笑)
会議の質は間違いなく上がると思いますw
教育改革の9割が間違い(諏訪哲二、2017)
文科省主導での教育改革の批判本。

理論の正しさばかりを重視し、実践まで考慮に入れていないため、そんな簡単なものじゃないよ、というのが主旨。
・アクティブ・ラーニングもそう簡単にいかない。学力がつくことの本質を踏まえるべき。
・教育は「行政のちから」「教師のちから」「民間のちから」「子どものちから」からなる
・時代の変遷とともに、このバランスが変わってきた。
・「教師のちから」が十分に発揮される体制を構築すべきである
・《「子どものため」は教師のおごりである》という章で、カリスマ教師・堀裕嗣氏を批判している。
とても説得力のある論点整理をされていて、勉強になります。
自分が生徒なら、この距離感を保てる教師が好きです。距離感の近い教師は、無意識のうちに自分のことを好きになることを強要しているように感じてしまうからです。合わないタイプもいるので、そういう人はつらい。まあ、好みの問題でしょうね。
堀氏への批判については、どちらの方もレベルが高すぎる話をしているというのが私の印象。
感じ方のズレはお二人の性格の違い、そして、そこから派生する、教師と生徒の距離感の違いからくるものが大きいように感じる。
ただ、堀氏の著書に少し違和感を持つ人には、その理由の一端がわかるかもしれない。
【全体的な感想】
ここで紹介している著者の多くは、週末などに自主勉強会をしたり、執筆されたりと、本当に努力していらっしゃるのだと思いました。立派だと思います。
少しうがった見方をすると、「子どものため」はあるのでしょうが、「自分の楽しみ」の部分もあるのかなとも思います。気の合う仲間とのやり取りも楽しいでしょうし。いいことなんですけど。ただ、マジメだなと(笑)
教室では教師はある種「王様/女王様」のような立場だし、生徒の多くは王様/女王様に気に入られたい聴衆。
技術は磨かれるべきだが、落語家が「今日のはうけたな」と言うような感じの自分目線になっていないかの確認は必要でしょうね。
それでも先生が楽しんでやってくれる分には、生徒にとってはいいのでしょうが。
一方で、この手の自主活動をやっていない人との差はとても大きいのだろうなと思います。そして、やっていない人が圧倒的に多い?実態はどうなんでしょう。
アクティブ・ラーニングですが、どのように現場の学びが変わっていくのかが楽しみです。
方向性は、いいことだとは思いますが、クラスをする側の教師がこの手の授業を受けた経験がないでしょうから、どうやって教えるのだろう、確実に今までより高度な技術が必要となるだろうに…とやや心配になったりもします。
たとえば、一斉授業方式でもきちんとできない人がいる中、アクティブ・ラーニングの各種手法を学びに結びつけることができるのか?あるいは、疑念無しに変えていくことができるのだろうか?
考えすぎでしょうか。
アクティブ・ラーニングという言葉はかなり使われていますが、このような形で上から下りてきた言葉というのは、あっという間に手垢がついてきそうな気もします。
教育はやはりバランスじゃないかなと思います。「やれ、〇〇だ」「次は、アクティブだ」といった類の話にならないようにと今からおっしゃっている著者もいらして、
PS:プロに対する個人的な持論
今回は、「プロの技術」について話をしました。
プロにハートは重要ですが、ハートだけでもいけません。技術は大切ですが、それだけでもダメです。
頼れるピッチャーは、ハートをこめて、様々な球種をコースに投げ分けます。これが本物のプロでしょう。
芸人も同じです。
浅草演芸場で年寄相手に話すのか、若い女の子向けのテレビ番組でやるのか。それによって、ネタを変えるのか、同じネタでツカミを変えるのか。
一つの芸風だけでは、底の浅い芸人にしかなれません。年齢によっても変えていく必要があります。
(なんか芸人評論家みたいですね、私w)
そして、教師です。子どもの毎日や将来に影響を与える教師です。
時代を読みながら、プロとしてハートと技術を鍛えている方々が大勢いらっしゃいます。
難しい時代に入っていますが、頑張っています。応援しましょう。
今回の公教育の技術は、教育界だけではなく、コミュニケーションに関わる業界の方に有効です。まあ、他業界の方にとってはなかなか触手は動きにくいかも知れませんが、全ての業界の方にとって有効な知恵・技術を教えてくれる本と思います。
<堺谷武志の略歴>
大阪出身、京都大学工学部、南カリフォルニア大学MBA、三菱UFJ銀行を経て、キッズアイランド設立。保育士。一女の父。
現在「都会の子どもに『ソダチバ』を!」プロジェクト推進中
(プロフィール詳細はこちら)
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村