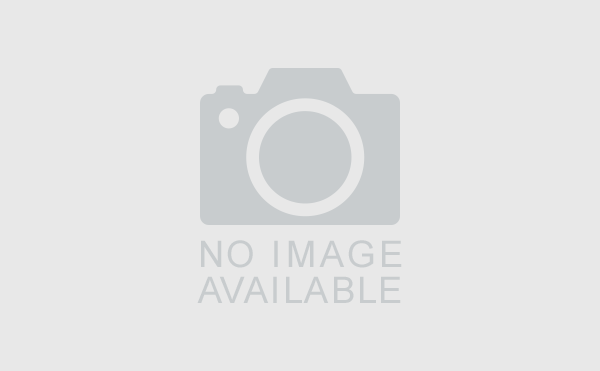子育てサプリ:発達段階(1~3歳)を理解しましょう①
小さなお子さんをお持ちのご家庭へ:これから発達段階についてはお話ししたいと思います(4回シリーズ)。
発達段階とは「各年齢における特徴」のことです。とても大切ですので、パパにも教えてあげてくださいね。
本題に入る前に前回の話のポイントを整理しておきましょう。
(前回はこちら:これでスッキリ!? 「性格」&「年齢」&「経験」の3つに分けてみる)
- 子育ての悩みが多いのは1~3歳。
- 「うちの子はなんで〇〇なのか」の疑問が発生。
- 子育てで煮詰まったら、「性格」「年齢」「経験」の3つに分けて考えてみるとよい。
- 「性格」と「年齢」は変えられないので、割り切ってあるがままを受け止める。そして、できること(=いい「経験」を与える)に集中する。
- 「年齢」の理解は、1~3歳頃の「発達段階」を理解することで、気持ち的にかなり楽になれることが多い。
→今回はこの「発達段階」の話となります。
1~3歳で大きく、大きく発達します
子育ての悩みの多くは、1~3歳児の特徴をよく知らないことが要因に思えます。
多くの方が、3歳児頃までの記憶はほとんどないでしょう。ですから、イメージがわきにくい時期なのですね。
それなのに、1歳から3歳間は、最も大きく変化する時期なのです。
「寝ころんでいた赤ちゃん」が「意見を言う子ども」まで、3年程度で一気に成長します。
それも、いくつもの「大人にはわかりにくいステップ」を踏みながら。
そこで、年齢ごとのだいたいの特徴を知っていると、
「1歳児って、こんなもんなんだ」とか
「2歳児だし、仕方がないよね」とか、
割り切ることができて、気持ち的に楽になれます。
「割り切る」という表現を使うと少し投げやりな表現に聞こえるかもしれませんが、そうではありません。
例えば、子どもが反抗期なのに同じようにこちらが意地になっても(これがまた親だと意地になりやすい)、解決しないことが多いのです。
で、つい怒鳴ってしまって、自己嫌悪に陥るというのはよく聞くパターンです。
全てを頭ごなしにしてはいけないのはわかっている。かと言って、全てをハイハイと言っていたら日々が回らない。
ですから、年齢毎の大きな特徴を理解しておいて、自分としてやるだけやったら、割り切る。周りに協力をあおぐ。これが行き詰らず、毎日を楽しむための現実的な対応だと思います。
昔は、こういう知恵(発達段階や対応方法)は、同居のおばあちゃんや近所のおばちゃんが教えてくれたり、間に入ってくれたり、サポートしてくれたりしたのかなと思うのです。
が、今は、少子化・核家族化の時代ですから、難しいことも多いと思います。
こういった「発達段階」は意識して学んでおくことが必要です。
発達段階(Developmental Stage)とは?
発達段階とは「各年齢における特徴」です。
厚生労働省発行の「保育所保育指針解説書」では「発達過程」とされています。
他にも市販本があるのですが、ほとんどが保育者向けのもので、また、表現が無難なので、
「1~3歳児のダイナミックな発達が伝わりにくいかな」というのが私の印象です。
キッズアイランドでは、米国Teaching Strategy社が発行するCreative Curriculum(以下、CC)で述べられている発達段階をベースにしています。
今回は、スクールでの経験やその他の知識を併せて、できるだけわかりやすい形でお伝えします。
発達は、便宜上大きく3つの分野に分けて述べます。
- 身体面(Physical Development)
- 社会・感情面(Socio-Emotional Development)
- 認識面(Cognitive Development)
今回は社会・感情面を中心に発達段階を説明していきます。
なぜなら、子育ての疑問の多くは、この分野の発達が大きく関係しているからです。
0~3歳に共通のキーワードは「アタッチメント」
0歳から3歳の時期に関するキーワードについて、私がひとつだけ挙げるように言われますと、それは「アタッチメント(愛着関係)」になります。
心理学者のジョン・ボウルビィ(John Bowlby)が提唱したアタッチメント理論によるもので、アタッチメントが長期的な成長・発達において重要であることは、様々な研究で指摘されています。ポイントは以下です。
社会・感情面の正常な発達には、一人以上の養育者(母のことが多い)との親密な人間関係が大切である。
子どもにとって「安全地帯」の役割を果たし、ここを起点として、外の世界を探検しにいく
アタッチメントの具体的な方法
アタッチメントというので、やはり身体的な接触(いわゆるスキンシップ)は大切です。
アイコンタクトとか他にもした方がいいことはたくさんあります。
が、何もかもというと大変なので、私から一番お勧めしたいことは、
できるだけたくさん話しかける
ということです。
何をどのように話しかけたらいいのか戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。その場合に、一番シンプルで簡単で有効な方法は、
まずは、子どもの行動や感情をそのまま描写すること(言葉にしてあげること)
です。
「泣いているのね。悲しいのね。」と抱っこをする
「怒っているのね。おなかがすいたのかな」と微笑みかける
「笑っているね。楽しいね」と体をタッチ、など
お世話をする時にせっかくなので、黙ってではなく、話しかけながらするといいと思います。
新人の保育士さんなども、ふと気づくと黙って淡々とお世話をしてしまっていたりしますが、とてももったいないです。
語りかけが大切というのは頭でわかっていても意外に難しい。なにせ忙しいですから。
何を話そうとか考えると、考えすぎてかえって黙りこんだりしてしまう(笑)。
そんな時は、子どもが今やっていることをそのまま言葉にしてあげるのがシンプルで、そして子どもの動作とリンクしているのでとても効果的です。
話ながらお世話をすると、アイコンタクトも声のコミュニケーションも必然的に増え、子どもも寄り添ってもらえている安心感を持つことができます。
そう、話しかけてあげることを意識すると、他で必要なこともたいていリンクしていきます。
語りかけの効用としては、認知的なスキルも押し上げるようです(ここをあまり強調すると、いやらしくなるのでサラッと言いますが…)
「乳幼児期の話しかけ」
→「幼児期での語彙の増加」
→「語彙の多い子は加速度的に語彙を増やす」というサイクルが発生します。
そして、語彙の多さは認知的・非認知的スキルの発達にもつながっていくことになります。
アタッチメントと話しかけは、ずーと大切になる考え方です。キーワードとして特に意識しておいてください。
話かけなきゃというのがストレスにならない程度にしてくださいね。
忙しい子育てママへの今日のポイント
色々申し上げましたが、今日のポイントとしてはこの1つだけ覚えてください。ここが全ての基本です。
子どもの動きを言葉にしてあげましょう。
次回以降は、各年齢についてお話します。
<次回、1歳児の特徴と対応、に続く>
<関連記事>これでスッキリ!? 「性格」&「年齢」&「経験」の3つに分けてみる
注意事項:
今シリーズはCreative Curriculumからの情報を活用しており、その国内翻訳権等を担っているラーニングネットワークの協力・許可を得て記載しています。従いまして、本ブログからの無断転用は禁じられていますのでご注意ください。変更しない形でのブログのシェアは全く問題ございません。
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村