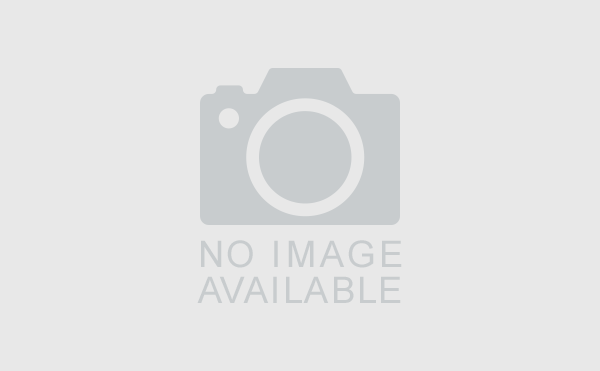書感:科学が教える、子育て成功への道
科学が教える、子育て成功への道
著者:キャッシー・ハーシュ=パセック*1、ロバータ・ミシュニック・ゴリンコフ*2
*1:テンプル大学教授、ブルッキングス研究所シニアフェロー、*2:デラウェア大学教授、「Child Development」編集委員
<感想>
- この本で紹介されている6Cはとてもよくできている(当たり前ですが)。親の気になるハードスキルだけでなく、かと言って、昨今流行りの非認知能力の大絶賛のみで終わらず、「両方のバランス・融合」を強調していて共感できた。
- Cにこだわったために語呂合わせの面は否めず、また、性質や重要度も違うと感じたので、自分なりに関係図をアレンジ。個人的には中でも3つに重点を置きたい。
- ①コンフィデンス(「物怖じ」せずに一歩踏み出せるか)、
- ②コラボレーション(グローバル化・多様化の時代において周りと協働できるか)、
- ③クリエイティブ・イノベーション(創造性もさることながら「まずやってみる」姿勢)
残りの3つは、これらを実行する際に助けとなる智恵やスキルと言ったイメージでとらえた。
- 日本人の得意分野(配慮、倫理観、まじめさ)がより大きなフィールドで花開くには、やはり「一歩前に出る。そして、やってみる」積極性が大切なことは間違いない。その意味で極論すると、全ての素は「コンフィデンス」かと思う。これが「自立」につながっていく。
- 幼稚園から小学校くらいまでもうちょっとワイルドでいいのではないか。キッズアイランドに来る年齢の子どもはみな「ワイルド」で「自信」にあふれている。(なのに、高学年くらいになると、いつの間にか手を挙げず、意に沿わなくてもひょこひょこお辞儀する子になってしまうのはなぜだ)
- 成長過程で多少の逆風の環境があろうと、揺らぐことのないコンフィデンスの根っこが定着するように「2歳から10歳まで一貫して、家庭と学校で自分らしさを徹底して受け止めて、そして『まずはやってみる』姿勢をサポートする『ソダチバ』」はやはり創るべし!である。
<本書からの抜粋(備忘録)>
| Collaboration | Communication | Content | Critical Thinking | Creative Innovation | Confidence | |
| Level 4 | それぞれの強みを活かし弱みを補い合う | 対話によって互いに満足するストーリーを作る | 専門領域について熟知し直感が働く | 根拠に基づき熟慮して上手に疑う | 変革についての大きなビジョンを持つ | 熟慮した上で失敗にひるまず挑戦し続ける |
| Level 3 | やりとりをしながら進める | 対話して他者の思い・考えを理解する | コンテンツ同士をつなげて考える | 色々な意見・立場をどれも正しいと捉える | 独自の「声」を発見する | 新しい取り組みのリスクを計算する |
| Level 2 | 横並びで勝手に進める | 一方通行でおしゃべりする | 広く浅く理解する | 自分の答えを絶対に正しいと信じる | 手段と目標を考える | 自分の実力を相対的に見極める |
| Level 1 | 自分自身が全て仕切る | 感情のままに行動する | 特定の状況について限定的に理解する | 見かけをそのまま信じる | とりあえず試す、やってみる | 根拠なき自信を抱く |
- 著者の「成功」の定義:「健康で、思慮深く、思いやりがあり、他者と関わって生きる幸せな子どもを育て、皆が他者と協力し、創造的で、自分の能力を存分に発揮する責任感あふれる市民となる」こと
- 「成功」のためにカギとなる能力として6Cを提唱し、学びに不可欠と主張
- 6Cにより「ハードスキルとソフトスキルを絶妙に融合する」(どちらかだけでもいけない)
- 国連事務総長「教育についての国際指針」:「世界は地球規模で解決が求められる大きな課題に直面している。相互に関わりを持つ地球規模の挑戦は、全ての人々の尊厳のために、私たちがどう考え、行動するか、大きな意識変革を要求している。一人ひとりが、読み、書き、計算できるようになるだけでは、教育の目標として不十分だ。教育は変わり続けるものであり、重要な価値観を生み出すものである。…教育は、また、私たちの日々の生活につながる大きな問題について答えを出すものでなければならない。
- ダニエルピンク著「ハイ・コンセプト」:「これまでの数十年間は、コードを書くことのできるコンピュータのプログラマー、契約書を作成できる弁護士、財務の数字に強いMBA保持者のような、ある分野に精通した特定の人たちが世の中を動かしていた。しかし、そんな時代は過ぎ去った。未来はこれまでとは全く異なる心を持った人たちが動かしてゆく。それは創造性あふれる人、共感力の高い人、パターンを見つけられる人、そして意味を作り出す人である。芸術家、発明家、デザイナー、物語の作り手、人の世話をする人、元気づける人、そして大胆な構想を考えられる人が、社会において大きな報酬と大いなる喜びを得るのだ。
- コラボレーション:他の人と共に働くのはヒトだけに許された特権
- 人類学者キム・ヒル:「人類が特別で宇宙ロケットを作り出すまでに至ったのは、大きな脳を持っているからではなく、一万にも及ぶ個人が協力して知を生み出すことができたからだ」
- トマセロ「ヒトはなぜ協力するのか」:ともに働き、学ぶことで多くの利益がもたらされた。コラボレーションするこそこそ動物界において私たちを際立たせている行動基準
- 一緒に仲良くビールを飲むのはコラボレーションではない。コラボレーションは規律であり、自制心である。
- 演劇が役に立つ
- コミュニケーション:グローバル時代は高いコミュニケーションスキルが必要
- 相手を尊重しながら、話し、聴き、書き、説得的に議論するスキル。どんなによい考えであっても声に出して自分の言葉で訴えない限り、他者の心は動かせない。
- グローバル化に伴う多様化の時代、対話を超えてつながるサイバー空間において、より高いレベルのコミュニケーションスキルが必要
- 全ては対話から始まる
- コンテンツ:私に話すなら私は忘れる。私に教えるなら私は覚える。私に関わらせるなら私は学ぶ(ベンジャミン・フランクリン)
- 学んだことを深く、高いレベルで理解するには、演劇が有効。役柄と場面の関係、登場人物と現実世界との関係。なりきることによる共感する力、等
- 良い学びが起きる条件:自ら率先して行い、没入して関与し、意味を見出し、社会的に関わり合うことは子どもを深い学びへと誘う。
- マルコム・グラッドウェル著「天才!」:一万時間ルール(才能に準備が伴って初めて達成することができる)。
- インドの哲学者ジッドゥ・クリシュナムルティ:教育に終わりはない。本を読むのはテストに合格するためでも、教育を終えるためでもない。生まれてから死ぬまで、私たちの全生涯が学びのプロセスなのである。
- クリティカル・シンキングの定義:「疑わしきときは根拠を求めよ」「理に適った妥当な判断」
- ジェフ・ベゾス:「異議を唱える勇気を持ち、一度決定したことには全力で取り組む」
- クリエイティブ・イノベーション:これからは「我想像する、故に我あり」の時代
- マークランコ著「創造力」:「誰もが創造力を発揮できるポテンシャルを持っているが、全員がそのポテンシャルを活かしているわけではない」
- 遊びと創造性の専門家サンドラ・ラス:「遊びこそ創造力の源泉で(中略)子どもは何もないところから何かを作る」
- 大人は子どもの遊びに火をつける存在にも創造的に表現する方法を邪魔する存在にもなりうる。より創造的な子どもを育てるには子どもの独立を助け、色々とやらせる方がよい。
- デザインカンパニーIDEOティム・ブラウン「想像力を発揮するためのルール」: 「すぐに判断するな!」「(アイディアを出すときは)とにかく沢山出そう!」そして、「すぐにアイディアをプロトタイプとして形にする」
- コンフィデンス:「失敗は成功に到達するまでの道しるべである」(C・S・ルイス)/ 「夢を大きく。失敗覚悟で挑戦しろ」(冒険家ノーマン・ボーン)
- 自信には2つある。①試してみようという意志(「何もしなければ100%失敗する」) ②粘り強く続けようとすること(アンジェラ・ダックワース「GRIT」:長期的な目的に向かって挑戦し続ける情熱と粘り強さとスタミナがあること)
- レベル1として「根拠なき自信」を抱く~未熟だから粘り強い すべてを理解しているという幻想から自信は育つ
- フロリダアトランティック大学デビッド・ビョークランド:「人間の子ども期間が長いのは長い生涯を生き抜くために必要なことをじっくり身につけるためだ。認知的に未発達だからこそ粘り強く取り組む自信が生まれ、適応に時間をかけることができるという選択を人類は進化の結果、手にしたのである」
- 自尊心が低いとリスクが取れない。未就学児は自尊心が高く、学校に入って他社と比較するようになると徐々に低下する。小学4年生頃から再び上昇し、中学・高校になると急降下する。
- 過保護は自尊心を損なう。リスクを取る自信を育てるには、子どもがリスクを取り自分の限界を知る練習をする余裕が必要。どこまでは成功でき、どこからは失敗してしまうのか、その境界を知る。子どもがスムーズにすべてできるようにおぜん立てする「過保護な親」は子どもが自尊心を育てるのを阻害する。
- 自信に養うには芸術に触れる。正解はなく、自分なりに考えざるを得ない。①没入し、持続する、②ビジョンを持つ、③表現する。すると振り返る目が育つ。
- 自信を養うには(1):子どもが難しい課題に直面した時、すぐにうまくいかなくても試行錯誤し続けるように励ます。新しい物事に挑戦し、あれこれ試し続けることを称賛する。褒めるのは、子どもの能力、頭の良さではなく、努力である。
- 自信を養うには(2):子どもの気質の違いはやはり無視できない。ある子供はリスクのある状況でも積極的にチャレンジする。一方、どんなに励ましても、自分が最初にやることはなく誰かが先に試すのを待つ子もいる。
- 失敗覚悟で挑戦する:挑戦し続けて成果を出すには失敗が必要。失敗は色々と比較しながら、何がうまくいき、何がうまくいかないか測定するための道具になる。
- クラスで6Cを活かす(大学での事例)
- グループで一緒に作業し、グループ発表、グループプロジェクトに取り組む(コラボレーションする力を育てる)
- 論文を読んで論評する課題を出し、また試験で高度の文章表現力を要求し、調査したことを口頭でプレゼンテーションさせ、授業中の議論にどれだけ参加したか評価する(コミュニケーションの質を上げる)
- 「デジタル時代を生きる」「モラルの心理学」のようなトピックについて主要な論文を読む(知識コンテンツを豊かにする)
- 読んだ記事でなされている議論を評価し、自分の意見を述べる筆記試験を行う(クリティカル・シンキングする力を高める)
- 自分の思い付きを調査して追求する(クリエイティブ・イノベーションを発揮する)
- 堂々と語れる場を設定し、仮説が間違っていたり、失敗したりしても粘り強く取り組むように応援する(コンフィデンス=自信を高める)
- 「ガイドされたプレイ」を仕掛ける
- 子どもの興味や関心を探り、子どもの問い反応し、子どもが知りたいと思っていることを語り、子どもが問いを追究していくのをサポートするのが私たち大人の役割である。(教えたがりの大人は「百害あって一利なし」)
<堺谷武志の略歴>
大阪出身、京都大学工学部、南カリフォルニア大学MBA、三菱UFJ銀行を経て、キッズアイランド設立。保育士。一女の父。週末登山家。
現在「都会の子どもに『ソダチバ』を!」プロジェクト推進中
(プロフィール詳細はこちら)
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村