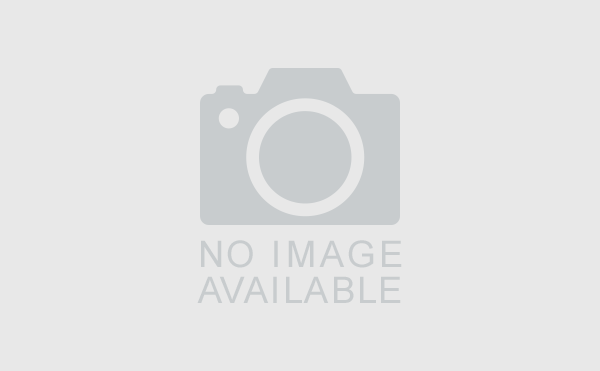バイリンガル教育:大人の英語力アップ(後編)
英語のハウツー本は、英語大好き人間(英語講師や専門家)が書いていることが多いです。
ですが、世の中英語好きばかりなわけではありません。実は、私も「英語は(特に好きではないけれど)必要だから」というタイプでした。
途中で無理に好きになる努力を止めて、割切って「多少つらくても、効果のある方法」に切り替えました。
前編では、主にリスニング(シャドイング)方法と教材についてご紹介しています(前編はこちら)
後編では、今回スピーキング、リーディング、ライティングなどをご紹介します。
スピーキング: そんなに簡単にしゃべれるようにはならない
スピーキングは難しいですね。
言いたい内容、話す相手によって表現も変わってきますので。
最終的には、
-
言いたいことを英訳する→(ネイティブに)チェックをしてもらう→覚えて使ってみる
-
シャドイングなどで気に入った表現を単語帳に書き出しておいて、丸暗記しておく
の方法の組合せで対応しました。
内容に加えて、ディスカッション等に参加となると、一定のスピードも必要になってきます。
話したい内容が明確なら事前に準備して、練習しておきましょう。特にプレゼンは準備が全てです。
ただし、準備ができない状況もあると思います。Q&Aやディスカッションの場ではそうです。
そういう場合は、開き直って知っている単語をつなぎ合わせて、必死に伝えましょう。それしか方法はありません。
わからないという勇気
コミュニケーションと言うものは、スピーキング単体で成り立つわけでなく、
・相手の意図をつかむ
・こちらの意図を伝える
が繰り返されていくものです。下手でも意図をつかんで、意図を伝えられれば勝ちです。
難しいのが、話すこと自体よりも、相手の意図をつかむということです。
そのための手段として(目的ではなく)リスニング力が必要になります。
実は、自分のコミュニケーションスキルが上がれば上がるほど大切だと
強く感じるようになってきた表現は以下のようにとてもシンプルな表現です。
Say that again, please?
Please speak more slowly.
あとは表情やしぐさで I don’t understandをアピールするとか、
要は、「わからん」ということを伝える表現です。
実は、これによって相手からの信頼度は上がると思っています。
少なくとも、こいつは知ったかぶりをしないということは相手に伝わりますから。
「わからなくてもわかったふりをする日本人特有のお作法」が、
グローバルなコミュニケーションの場ではマイナスに働くことはよく意識しておきましょう。
だから、勇気をもって言うんですよ。 最重要表現をできるだけ早い段階で、できるだけデカい声で!
Could you please speak more slowly?
スピーキング対策に効果的だった教材トップ3
スピーキング基礎力向上のための教材をご紹介します。
発音編: Mastering the American Accent
発音は、前回のリスニング教材番外編でもご紹介したこの本です(詳細は前回ブログをご参考ください)
語彙編: 英単語ピーナツほどおいしいものはない 金メダルコース
私は、ボキャブラリーの勉強が嫌いでなりませんでした。今も嫌いです。
・話し言葉と書き言葉が混じってリストアップされていて、どんな状況で使えるのかあやふや。
・レベルが上がるほど、生の英語で出くわす確率が落ちてくるので、覚えても報われている感じがしない。
・一定レベル以上になると、テスト対策以外で覚える必要があると感じられない。等々…
その中で、一番良かった(ましだった)のが「ピーナッツ」シリーズです。

シンプルなんですが、ストレスが一番少なく、頑張ってみようと思えたのです。
銅メダルから金メダルまで、レベルに合わせて試してみて下さい。
コツは、一日にできるだけたくさんを一気に覚える(そして、すぐに忘れる)、を繰り返すことでした。
性格によって違うでしょうが、変にまじめに取り組まないことをお勧めします。
忘れても気にしない、気にしない。また覚えればいいのですから。
ただ、スピーキングに使う場合はできるだけシンプルな言葉を使った方がいいと思います。
会話編: やっぱりシャドイング!
タイトルでいいのがあると会話本をつい買ってしまうのですが、何度もはめられました。
というより、私は正直この手の勉強は苦手です。
どういう局面で使えるのかよくわからない表現を覚える行為にモチベーションが上がりませんし。
シンプルなのは、NHKのラジオ・テレビ講座です。
これを毎日できる人はそれだけで天才です。私はできませんが正統派だとは思います。
私の場合は、海外ドラマのシャドイングで抜き書きして覚えるのがしっくりきました。
主人公が言っていた表現とか、シチュエーションがリアルなので、状況的にも変な英語じゃないだろうと思って使えるからです。
リーディング: シャドイングがリーディングの役割も果たす
リーディングについては、いつの間にか消滅、みたいなことが多かったです。
私は日本語の読書は好きで、よく読むほうだと思います。
英文だと、時間当たりに得られる情報量が少なくて、飽きてしまうんですねー。
和訳があればそっちをザーッと読む方が効率的。
多読は効果があるようです。
私は続きませんでしたが、小学生~中高生の間に部活みたいな感じでやれるところがあれば楽しそうです。
結局は、ここでもシャドイングでスクリプトを読むことがリーディング強化にもなりました。
読めるスピード以上では、聴けない
黙読で理解できるスピード以上の速さで話されると、脳がついていきません。
リスニングの能力とリーディングの能力はこんなところで深くリンクしています。
ナチュラルスピードで話されている英語のスピードが、最低限必要な黙読スピードだと言えます。
せっせとシャドイングしましょう。
要は、「音」なのです。リーディングもアルファベットで、これは表音文字なので「音」なのです。
ですので、英語は無理に4技能に分けるのではなく、「音」と「意味」をトータルとしてつかんでいく訓練が大切です。
興味も必要性も低い場合、シャドイングに重点配分することでカバー可能だと思います。
ライティング: ほぼやらず
ライティングについては、ほぼ何もやりませんでしたし、できませんでした。
私は、ライティングは手間がかかり、習得するのに最も大変な技能だと思っています。
契約書などの正式文書や特殊なレターは外部に委託すべきだと思います。
とすると、自分で書く必要性があるのは、Eメールやパワーポイント作成程度です。
レターや簡単な契約書であれば、今はインターネットでひな形がいくらでも手に入ります。
この方法が手っ取り早いと思います。
本格的なライティングは基本的には今でも得意ではありませんが、
実用的には、ネットや周りの力も借りながら対応すれば、まあ何とかなります。
限られた時間です、「割り切ってやらない」というのも1つの考え方です。
実践英語: 持てる力を総動員する
実践的な英語について話してきていますが、これは2つに分かれます。
例えば、仕事などで必要な場合、
今持っている英語力でコミュニケートできるようにとにかく凌ぐ
凌ぎつつ、地力をつけていく
ということになります。
これまでは主に後者の話をしてきました。
ですが、「仕事は、英語ができるようになってからね~」というわけにはいきません。
持てる英語力で凌ぐしかありません。
・日本語でいいので、その分野の本を複数読んで勉強をしておく。
・関連すること(法律や税務など)は、日本語で理解し、英語でキーワードを覚えておく。
・準備してできるだけペーパーに落として、それで説明するようにする
・相手にバカにされないように堂々と振舞う、そして、相手を尊重して謙虚な姿勢になる。
・わからなければわからないと言う。
・議事録などできるだけ文書に落とすように(できれば落としてもらうように)する。
・あとで調べて確認する。などなど
こう見ると、英語以外でできる工夫はいくらでもあります。
英語の技術的な部分にとらわれ過ぎると、仕事のトータルとしての仕上がりが悪くなります。
実践で使わざるをえない状況に直面したら、英語力のなさを嘆くのではなく、
とにかく今ある英語力で凌ぎながら、成果を上げるために全力を尽くすというのが、実践英語の本質だと思います。
<関連記事>
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村