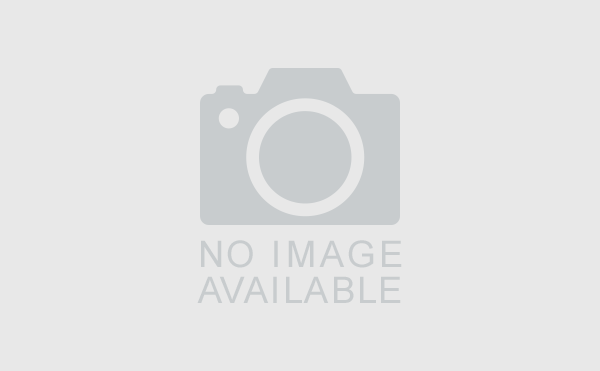書評:外国語運用能力はいかに熟達化するか ~言語情報処理の自動化プロセスを探る
この本では「英語の自動化(ペラペラにしゃべれるようになるには?)」をテーマに、言語学者、脳科学者、学習科学者など15名が共同研究されています。
学際を越えてチームを組み、丁寧に厳密に科学的なアプローチをされているのが素晴らしいです。

備忘録的に「こんな感じかな」という私なりのざっくりとした理解をまとめておきたいと思います。学者さんたちの厳密性をズタズタにしていると思います、申し訳ございません。
習得の仕方に関して、科学的にほぼ言い切れること
- 子どもの場合、繰り返し能力が高い子どもほど、外国語習得能力も高い。
- 単語は、口頭反復をすると覚えやすい。
- 文章については、黙読(または整序)後、見ないで反復すると覚えやすい。
- シャドイングは、(単なるオウム返しではなく)意味把握や発音でも意義がある。
流ちょうになること(自動化)に関して、科学的にほぼ言い切れること
- 「なんとか理解できる」と「ペラペラにしゃべれる」の間には、脳内で活動する部位が異なるくらいの大きな差がある。→これは大きな発見かと。
- 「なんとか理解」から「ペラペラ」に移行できるかの方法については、今後の課題
これらは私の現場感覚ともぴったりときました。
- 運営するプリスクールでも、繰り返すのが上手な子は伸びる傾向にある。(あとは物怖じしないタイプの子ども)
- 個人体験としても、①シャドイング、②単語帳に表現を抜き書きしてチラ見で覚える、の2点は、様々試した中でも特に効果的な方法だったので、大いに同意できる。
個人的には、エピローグをとても興味深く感じました。
・言葉と脳の働きの関係を科学的に解き明かすのは、やはり簡単ではないのだなということがわかった。
・なんとか科学的に裏打ちしたいという情熱と、脳を扱うという手法の制約とのハザマで熱く知的格闘をしていらっしゃる方々がいて心強く感じた。
・日本の学界も公用語が英語で、論文以外にも、発表や質疑応答などが必要。理系の世界での英語技能はすでに現実化した世界。
・日本人被験者はリスニングが苦手なので実験方法が制約された、という生々しい話も印象深い。根本的に今の教育方法を変えないといけないのではという点は、全く同感。
・科学的に裏打ちされた「効果的な学習方法を世に示したい」という想いが伝わった。
・このエピローグは、3名の学者がカジュアルに「こんなアイディアはどうだろうか」と話をしている。日本の外国語習得研究に関する先進的研究者の頭の中を垣間見ている感じ。対談方式であるからこそ出てきた話。短いが、この部分を読むだけでも大きな価値はある。
全体を通しての感想
・現在の日本の言語習得に関する先進的な研究が俯瞰できる素晴らしい本だと思いました。
・科学的な裏打ちを追及する姿勢は素晴らしいが、厳密性を追いかけるほど証明に時間がかかる。
・その間にも、公教育の現場で迷いの中で試行錯誤が続き、民間でも玉石混交の教材・言説が出回ることになる。日本全体としての非効率性・デメリットは小さくはない。
・それぞれの編著者は、現場経験からすでに「効果的な方法論」のアイディアはお持ちかと思います。議論を深めて「新しいトレーニング方法(仮説)」を作って、コソッと教えていただきたい(笑)。
・冗談をさておき、それらを①クラスで行うグループ学習と②自主トレ、の2本立てにして入門書を書いていただければ、みんな大喜びだと思います。
・最後になりましたが、本書は、外国語教育に関わる方は必読です!(ただ、ちょっとモデルと用語は専門的です)
著者・堺谷武志が運営するプリスクールは「キッズアイランド」はこちら
著者・堺谷武志の個人Facebookページはこちら
お気軽にお友達申請してください。ブログの更新情報やその他趣味の山登りについて等も投稿しております!
ここまでお読みいただき、まことにありがとうございます。 応援していただける方は、以下のボタンを押していただけると助かります(サイトに飛びますがそれだけで、清き一票と数えられます)
にほんブログ村